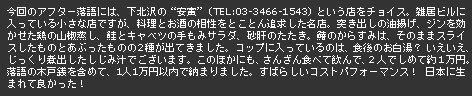|
ここ3〜4年、月に1〜2度、落語を聴きに行くのが楽しみのひとつになっています。毎月、定期的に通っているのは、有楽町のマリオンで催される「朝日名人会」。前座さんから始まって、総勢6人の落語をたっぷり聴くことができます。これで木戸銭は4,300円というのですから、日本の大衆芸能はすばらしい!
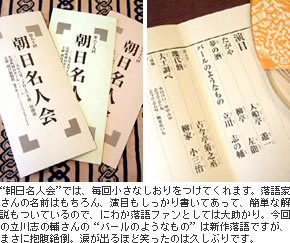 会のスタートは14時からと決まっていて、終わりはだいたい17時〜17時半。途中で、おなかがぐ〜っと鳴ると切ないので、行きがけに遅めのお昼ご飯を、しっかり詰め込んでいきます。
会のスタートは14時からと決まっていて、終わりはだいたい17時〜17時半。途中で、おなかがぐ〜っと鳴ると切ないので、行きがけに遅めのお昼ご飯を、しっかり詰め込んでいきます。
なのになのに、およそ3時間の高座が終わってみると、おなかはペコペコ。どうして〜?
普段、私はそれほど大食漢というわけではありません。もちろん若い頃には、山盛りのどんぶり飯までペロリと平らげ、定食屋のおばちゃんに「普通のOLさんたちは必ず残していくのに、ご飯もおかずも、全部きれいに食べてくれてうれしいわぁ」と喜ばれた時代もありましたが、今はとても無理。おやつの習慣もまったくないので、15時頃に撮影の試食をしたり、打ち合わせでちょこっとしたお菓子などをいただいたりすると、夜までまったくおなかがすかない、というていたらく。にもかかわらず、こと、アフター落語に限っては、どうしたことか? 我ながら常々不思議に思っていたところ、先日、池波正太郎の“さむらい劇場”という小説を読んで、ハタと膝を打ちました。その中で、老和尚が主人公の若いお武家さんに、こう語るのです。
「人というものは、物を食べ、眠り、かぐわしくもやわらかな女体を抱き、そして子をもうけ、親となる…つまり、そうしたことが渋滞なく享受出来得れば、もうそれでよいのじゃ。しかし、それがなかなかにむずかしい」
そう、確かにむずかしい。でも、とかく複雑に見える世の中にあっても、本来、人間というものはシンプルに生きる喜びを、身体が知っているような気もします。たとえば、落語に耳を傾け、アハハと屈託なく思い切り笑い、時には人情話にホロリと涙をこぼし、終わってみれば「あぁ、楽しかった」と思わず声が出て、気持ちがスコーンと抜けると、次には、おなかがすくといったように…。
笑って、泣いて、おなかがすいて、ご飯を食べて。その繰り返しは単純なものですが、人生それで、いやそれこそがいいんじゃないかと、妙に納得。落語ビフォーアフターには、人生のサイクルがギュッと濃縮されている気がします。
|
 |
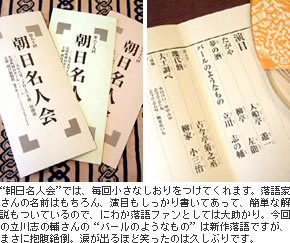 会のスタートは14時からと決まっていて、終わりはだいたい17時〜17時半。途中で、おなかがぐ〜っと鳴ると切ないので、行きがけに遅めのお昼ご飯を、しっかり詰め込んでいきます。
会のスタートは14時からと決まっていて、終わりはだいたい17時〜17時半。途中で、おなかがぐ〜っと鳴ると切ないので、行きがけに遅めのお昼ご飯を、しっかり詰め込んでいきます。